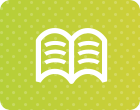相続コラム
夫婦間の相続税とは?配偶者控除は最低1億6,000万円まで非課税
投稿: 更新:

「夫婦間で相続税はかかる?」
「相続税を最小限に抑えたい」
「家族の将来の経済的安定を確保したい」
上記の疑問をお持ちの方は、相続を巡って家族間に争いが生じることを避けたいと思っているのではないでしょうか。
一方で、自身の突然の死去に備え、家族の将来の経済的安定を確保したいと考えるならば、配偶者控除についてよく確認をしておくのがおすすめです。
相続税対策が不十分で、多額の相続税を支払うことになる前に行動していきましょう。
本記事では、「夫婦間の相続税について、配偶者控除の基本や計算方法」を紹介します。
相続税の配偶者控除を利用する際の注意点まで紹介しているため、ぜひ最後までご覧ください。
【目次】
夫婦間の相続税と配偶者控除の基本
夫婦間の相続税と配偶者控除の基本を、以下に紹介します。
- 夫婦間でも相続税はかかる
- 相続税の配偶者控除とは
- 配偶者控除は最低1億6,000万円まで非課税
それぞれ解説します。
夫婦間でも相続税はかかる
夫婦間の相続でも、一定の条件を満たさない場合には相続税が課されるケースもあります。
相続税は遺産を取得した人ごとに課税される仕組みであり、配偶者が相続する財産についても例外ではありません。
ただし、配偶者控除という特例があり、1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額までは非課税となります。
控除を適用するためには、被相続人の法律上の配偶者であることや、相続税申告期限内に遺産分割を完了し、税務署へ申告書の提出が必要です。
相続税の配偶者控除とは
相続税の配偶者控除は、配偶者が相続した課税対象の財産にかかる相続税を大幅に軽減する制度です。
配偶者が相続した遺産額が、1億6,000万円または法定相続分相当額のいずれか多い金額までは相続税がかかりません。
配偶者控除は、遺された配偶者の生活基盤を守るとともに、夫婦で築き上げた財産に対する配偶者の寄与を考慮して設けられました。
配偶者控除を利用すると、多くのケースで配偶者の納税額はゼロ円になります。
また、相続税の配偶者控除については、下記の記事で解説しています。
詳細は「相続税の配偶者控除とは?適用要件と損をしないための注意点を解説」をご覧ください。
配偶者控除は最低1億6,000万円まで非課税
配偶者控除によって、配偶者が相続した遺産のうち、「1億6,000万円」または「法定相続分」のいずれか多い金額までが非課税となります。
そのため、配偶者が相続する遺産が1億6,000万円以下であれば、相続税は発生しません。
たとえば、遺産総額が2億円の場合、配偶者の法定相続分は1億円となるため、配偶者控除によって1億円分は非課税となります。
さらに、遺産が4億円あった場合でも、配偶者の法定相続分に該当する2億円までは非課税です。
ただし、制度を利用するためには、被相続人の法律上の配偶者であることや、相続税申告期限内に遺産分割を完了させる必要があります。
【配偶者控除】夫婦間の相続税の計算方法
夫婦間の相続税における配偶者控除の計算式は、以下のとおりです。
課税遺産総額の算出は、以下のとおりです。
- 相続財産の総額 – 基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)
配偶者の相続税額の計算は、以下のとおりです。
- 課税遺産総額 × 配偶者の法定相続分 × 相続税率 – 控除額
配偶者控除額の決定方法は、「1億6,000万円」または、「課税価格の合計額 × 配偶者の法定相続分)」のいずれか多い金額となります。
最終的な配偶者の納付税額は以下のとおりです。
- 配偶者の仮の相続税額 – 配偶者控除額
上記の計算式により、多くの場合、配偶者の納付税額はゼロ円になります。
相続税の配偶者控除の申告期限と手続き方法
相続税の配偶者控除の申告方法について、以下に紹介します。
- 申告期限と遺産分割
- 必要書類と申告手続き
ひとつずつ紹介します。
申告期限と遺産分割
相続税の申告期限は、被相続人が亡くなった日から10カ月以内です。
期間内に遺産分割を完了させ、配偶者控除を適用するための手続きをおこなう必要があります。
遺産分割が期限内に完了しない場合は、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出することで、3年以内に遺産分割を完了すれば配偶者控除を適用できます。
ただし、3年の延長は特例のため、できるだけ期限内に手続きを進めることが望ましいです。
遺産分割が完了したら、4カ月以内に更生の請求をおこなうことで配偶者控除を適用できます。
必要書類と申告手続き
配偶者控除を適用するためには、以下の書類を準備し、税務署に提出する必要があります。
- 相続税申告書(第1表から第15表のうち必要なもの)
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 遺産分割協議書の写し(法定相続人全員の印鑑証明書を添付)
- 相続財産の評価額を証明する書類(預金残高証明書、不動産登記簿謄本など)
- 配偶者の税額軽減に関する計算書(第5表)
これらの書類を揃え、申告期限内に税務署へ提出します。
相続税がゼロ円になる場合でも、配偶者控除を適用するためには申告が必要です。
手続きは複雑ですが、正確におこなうことで大きな税額軽減を受けられます。
夫婦間の贈与税と控除
夫婦間の贈与税と控除について、以下に紹介します。
- 夫婦間でも原則として贈与税はかかる
- 贈与税がかからないケース
- 贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)
それぞれ解説します。
夫婦間でも原則として贈与税はかかる
夫婦間の贈与でも、原則として贈与税の課税対象です。
年間110万円を超える財産の贈与があった場合、贈与税の対象となります。
夫婦で家計をともにしているため、贈与の認識は薄れがちですが、税務署は客観的な証拠をもとに判断します。
たとえば、マンションの名義変更で夫の持ち分を妻に無償移転した場合も、贈与税の対象です。
贈与税の納付や申告義務は、財産を受け取った側にあります。
相続税と贈与税については、下記の記事で解説しています。
詳細は「相続税と贈与税の違いを徹底解説:どちらを選ぶべきか?」をご覧ください。
贈与税がかからないケース
夫婦間の贈与でも、いくつかのケースで贈与税が課税されません。
年間110万円以下の贈与は基礎控除による非課税です。
また、夫婦間の扶養義務に基づくものとされるため、生活費や教育費の贈与が非課税となります。
ただし、高額な贈与物の場合は注意が必要です。
たとえば、高級時計のプレゼントが110万円を超える場合は、贈与税の対象となるケースがあります。
贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)
おしどり贈与は、婚姻期間が20年以上の夫婦間でおこなわれる特別な贈与制度です。
居住用不動産や購入資金の贈与に適用され、最大2,000万円まで非課税となります。
基礎控除と合わせると、2,110万円まで贈与税が発生しません。
ただし、適用には条件があり、贈与を受けた配偶者が該当の不動産への実際の居住が求められます。
また、相続税対策としても有効で、夫婦間の資産移転を効率的におこなえます。
相続税の配偶者控除を利用する際の注意点
相続税の配偶者控除を利用する際の注意点を、以下に5つ紹介します。
- 配偶者の所得制限
- 納税者本人の所得制限
- 内縁関係の配偶者は対象外
- 専従者給与を受け取っている場合
- 配偶者が死亡した場合
ひとつずつ解説します。
配偶者の所得制限
相続税の配偶者控除には、配偶者の所得に関する制限はありません。
ただし、所得税の配偶者控除と混同しないよう注意が必要です。
所得税の配偶者控除では、配偶者の年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)である必要があります。
納税者本人の所得制限
相続税の配偶者控除には、納税者本人の所得に関する制限はありません。
一方、所得税の配偶者控除では、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は適用できません
内縁関係の配偶者は対象外
相続税の配偶者控除は、法律上の配偶者のみが対象となります。
そのため、内縁関係や事実婚の場合はこの控除を受けられせん。
法律上の婚姻関係にあることが、配偶者控除適用の重要な条件です。
専従者給与を受け取っている場合
相続税の配偶者控除は、専従者給与を受け取っているかどうかに関わらず適用できます。
ただし、所得税の配偶者控除では、以下に該当する方は控除対象配偶者にはならないため注意しましょう。
- 青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人
- 白色申告者の事業専従者である人
配偶者が死亡した場合
配偶者が年の途中で死亡した場合でも、相続税の配偶者控除は適用できます。
ただし、申告期限までに遺産分割を完了させ、法律上の配偶者であることが条件です。
また、相続税の申告書を税務署へ提出することも必要です。
夫婦間の相続税に関するよくある質問
夫婦間の相続税に関するよくある質問をまとめました。
- 相続税がゼロ円になっても申告が必要ですか?
- 配偶者が全財産を相続した場合、子どもには相続税がかかりますか?
- 事実婚の配偶者にも相続税の配偶者控除は適用されますか?
- 配偶者が海外に住んでいる場合、相続税の控除は適用されますか?
ひとつずつ解説します。
相続税がゼロ円になっても申告が必要ですか?
相続税がゼロ円になる場合でも、申告は必要なケースがあります。
特例を適用した結果、相続税がゼロ円になった場合はゼロ円申告が必要です。
一方、相続財産が基礎控除以下の場合や、控除を使って相続税がゼロ円になる場合は申告不要です。
主な控除には、障害者控除、未成年者控除、相次相続控除などがあります。
申告が必要かどうかの判断基準は、以下の2つです。
- 相続財産を単純に計算して非課税枠を使っても相続税の対象となる
- 相続財産に特例を使って計算したら相続税がゼロ円になった
もし上記を同時に満たす場合、ゼロ円申告が必要となります。
また、相続税の申告が不要なケースについては、下記の記事で解説しています。
詳細は「相続税の申告が不要なケース|0円でも申告が必要な場合に注意」をご覧ください。
配偶者が全財産を相続した場合、子どもには相続税がかかりますか?
配偶者が全財産を相続した場合、子どもに相続税はかかりません。
ただし、配偶者の税額軽減を適用する際は注意が必要です。
たとえば、遺産総額が1億円の場合、全額を配偶者が取得すると相続税はかかりません。
一方、配偶者と子どもを法定相続分で分割すると、子どもが取得した5,000万円は課税対象となります。
遺産総額が2億円の場合、配偶者が全額取得しても1億6,000万円までは非課税となり、残りの4,000万円のみが課税対象となります。
もし子どもがいる場合は、将来の二次相続も考慮して相続の検討が重要です。
事実婚の配偶者にも相続税の配偶者控除は適用されますか?
事実婚や内縁関係の配偶者には、相続税の配偶者控除は適用されません。
配偶者控除は、被相続人の法律上の配偶者が負担する税額を大幅に軽減する特例です。
事実婚のパートナーは法定相続人とならないため、以下のようなデメリットがあります。
- 相続権がない
- 相続税の基礎控除額に制限がある
- 小規模宅地等の特例が適用できない
- 生命保険金の非課税枠が使えない
これらの理由から、事実婚の場合は相続税の負担が大きくなる場合もあります。
配偶者が海外に住んでいる場合、相続税の控除は適用されますか?
配偶者が海外に住んでいる場合であっても相続税の配偶者控除は原則として利用できます。
ただし、納税義務の範囲や課税される財産の範囲が個々の状況により異なります。
詳細については、国際相続に詳しい税理士に相談するのがおすすめです。
【まとめ】配偶者控除の最低ラインは「1億6,000万円」で覚えよう
夫婦間の相続税では、配偶者が相続した遺産のうち、「1億6,000万円」または「法定相続分」のいずれか多い金額までが非課税です。
また、夫婦間の贈与でも、原則として年間110万円を超える財産の贈与があった場合、贈与税の対象となります。
相続税対策が不十分の場合、多額の相続税を支払うことになるため、家族の負担やリスクが増加するため、早めに準備をおこないましょう。
もし相続税についてお悩みの方は、ぜひ翔和会計までお気軽にご相談ください。