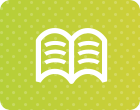相続コラム
相続税の無申告によるペナルティとは?見つかる理由8つと防止策4つ
投稿: 更新:

「相続税の無申告でペナルティはある?」
「無申告のリスクや罰則とは?」
「相続手続きを不安なくスムーズに進めたい」
上記の疑問をお持ちの方は、相続税の申告を適切におこない、無申告によるペナルティを避けたいと思っているのではないでしょうか。
自分で申告する必要があるのか判断できず、相続手続きを進めるなかで、無申告状態になることへの恐れが出てくるのはよくあるケースです。
しかし、相続税の無申告のままでいると、ペナルティが発生してしまいます。
本記事では、「相続税の無申告によるペナルティについて、見つかる理由8つと防止策4つ」を紹介します。
相続税の無申告による時効期間と適用条件まで紹介しているため、ぜひ最後までご覧ください。
【目次】
相続税の無申告に関するペナルティ4つ
相続税の無申告に関するペナルティは、以下の4つです。
- 延滞税
- 無申告加算税
- 重加算税
- 過少申告加算税
それぞれ解説します。
延滞税
延滞税は、相続税の申告納税期限までに納付しなかった場合に課されるペナルティです。
納付期限から原則として適用される利率は、以下のとおりです。
- 2カ月以内:年7.3%※令和4年1月1日から令和7年12月31日までの期間は、年2.4%
- 2カ月以降:年14.6%※令和4年1月1日から令和7年12月31日までの期間は、年8.7%
たとえば、相続税180万円に対して、申告期限から1年半後に申告した場合の延滞税は以下のとおりです。
- 2カ月以内の期間(61日間):180万円×2.4%×61日÷365=7,219円
- 2カ月超の期間(1年半-2カ月=487日間):180万円×8.7%×487日÷365=208,466円
- 上記2つの合計:7,219円+208,466円=215,685円
ただし、100円未満切り捨てのため、延滞税は215,600円となります。
延滞税を避けるには、できるだけ早く正確に申告納税することが重要です。
無申告加算税
無申告加算税は、相続税を申告期限までに申告しなかった場合に課されるペナルティです。
税務調査の事前通知を受ける前に自主的に申告した場合は5%、税務調査を受けてから申告した場合は10%(50万円を超える部分は15%)の税率が適用されます。
また「相続税がかかると思わなかった」「対象になると知らなかった」といった理由は、正当な理由とはみなされず、無申告加算税が課されます。
ただし、期限後1カ月以内に申告するなど一定の条件を満たせば、無申告加算税が課されない場合もあるためよく確認が必要です。
重加算税
重加算税は、故意に財産を隠ぺいしたり、虚偽の申告をおこなったりした場合に課される最も重いペナルティです。
申告はしたが財産を隠して過少申告した場合は35%、申告自体をしなかった場合は40%の税率が適用されます。
さらに、過去5年以内に同様のペナルティを受けたケースでは、それぞれ10%上乗せされます。
たとえば1,000万円の相続税を無申告で隠ぺいした場合、400万円の重加算税が課されます。
加えて、延滞税も加わり、最終的に50%近い追加負担となるケースもあるため注意が必要です。
過少申告加算税
過少申告加算税は、相続税の申告額が実際より少なかった場合に課されるペナルティです。
税務調査の事前通知前に自主的に修正申告した場合は、0%となります。
事前通知後に修正申告した場合、50万円以下の部分は5%、50万円を超える部分は10%です。
たとえば、1,000万円の相続税を500万円と申告し、税務調査後に修正申告した場合、合計47.5万円のペナルティとなります。
追加納付額500万円に対して、50万円までは5%(2.5万円)、残り450万円に10%(45万円)の過少申告加算税が課されます。
相続税の無申告とは
相続税の無申告について紹介します。
- 相続税の無申告の定義
- 相続税申告が不要なケースもある
ひとつずつ解説します。
相続税の無申告の定義
相続税の無申告とは、被相続人の死亡を知った日の翌日から10カ月以内に申告・納税をおこなわなかった状態を指します。
相続税の申告が必要なケースは、相続財産の総額が基礎控除額を超える場合です。
基礎控除額の計算方法は、以下のとおりです。
- 3,000万円+600万円×法定相続人の数
たとえば、法定相続人が2人の場合、基礎控除額は4,200万円となります。
相続財産がこの金額を超えると、申告義務が生じます。
一方で、配偶者控除や小規模宅地等の特例を適用すると相続税がゼロ円になる場合でも、申告が必要なケースにあるため注意しましょう。
相続税申告が不要なケースもある
相続税申告が不要なケースは、主に3つあります。
- 相続財産の総額が基礎控除額以下の場合
- 相続財産が3,000万円以下の場合。法定相続人の数に関わらず申告は不要
- 基礎控除以外の各種控除を適用して税額がゼロ円になるケース
ただし、注意が必要なのは、基礎控除を超える相続財産があっても、特例を適用すると相続税がゼロ円になる場合です。
このケースでは申告が必要となるため、たとえば、配偶者の税額軽減の特例を使う場合は、相続税がゼロ円でも申告をおこなわなければなりません。
相続税の無申告が見つかる理由8つ
相続税の無申告が見つかる理由は、以下の8つです。
- 税務署の調査活動
- 銀行口座の動き
- 不動産の名義変更
- 第三者からの通報
- 生命保険金の支払い報告
- 市区町村役場との連携
- 贈与や取引履歴の照会
- 相続財産の目立つ使用
ひとつずつ解説します。
税務署の調査活動
税務署の調査活動は、相続税の無申告を見つける主な手段です。
税務署はKSK(国税総合管理)システムを活用し、納税者の情報を一元管理しています。
過去の所得税や固定資産税の情報、死亡までの収入や所有不動産など、被相続人に関するあらゆる情報の把握が可能です。
もし被相続人の死亡届が市区町村役場に提出された場合、翌月末までに税務署へ情報が伝達されます。
銀行口座の動き
銀行口座の動きは、相続税の無申告を発見する重要な手がかりです。
税務署は、被相続人の銀行口座を調査する権限を持っています。
生前の資産状況や相続発生後の資金移動を把握できるため、預金残高や入出金履歴、大口の引き出しなどが調べられます。
たとえば、相続直前に多額の現金を引き出していた場合、隠し財産の存在が疑われるケースが多いです。
また、相続後に相続人の口座に大きな入金があれば、申告漏れのケースがあります。
不動産の名義変更
不動産の名義変更は、相続税の無申告を発見する重要なヒントです。
相続した不動産の名義変更手続きは、法務局でおこないます。
一方、税務署は法務局と連携しているため、相続による名義変更がおこなわれると把握が可能です。
また、固定資産税納税通知書や名寄帳(固定資産課税台帳記載事項証明書)を確認することで、被相続人名義の不動産を特定できます。
これらの情報をもとに、税務署は相続税の申告状況を確認し、無申告の可能性を調査します。
第三者からの通報
相続税の無申告が発覚する要因として、三者からの通報があります。
税務署は、メール・電話・手紙・面談の4種類の窓口を用意しており、いつでも情報提供を受け付け可能です。
たとえば親から多額の生前贈与を受けた場合、当初は秘密にしていても、不自然に多くのお金を持っていることを兄弟が疑問に思い、親に確認して事実を知る場合があります。
また、知人との会話で「祖父母からもらったお金で新車を購入した」などと話すだけでも、聞いていた人が通報するケースもあります。
生命保険金の支払い報告
生命保険金の支払い報告は、相続税の無申告が発覚する要因です。
生命保険会社は、被相続人が死亡し保険金を支払った場合、「支払調書」を税務署に提出する義務があります。
報告によって、税務署は保険金の受取人と金額を把握し、相続税の申告状況を確認します。
たとえば、法定相続人が受け取った死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が適用されますが、この枠を超えた分は「みなし相続財産」の課税対象です。
市区町村役場との連携
市区町村役場との連携は、相続税の無申告を発見する重要な手段です。
相続税法第58条により、市区町村は死亡届を受理した場合、翌月末日までに税務署へ通知する義務があります。
たとえば、5月15日に死亡届が提出された場合、6月30日までに被相続人の死亡日や保有不動産などの情報が税務署へ通知されます。
税務署は独自のシステムを使って、被相続人の生前の収支状況、所有不動産、株式などの資産状況、売買履歴を確認可能です。
贈与や取引履歴の照会
税務署は、被相続人の生前3年以内の贈与や、不自然な資金の動きを調査します。
相続開始前3年以内の暦年課税による贈与は、基礎控除110万円に関係なく、相続税の課税対象です。
また、税務署は国税庁のデータベースと外部機関からの情報を照合し、不自然な資金の動きを発見します。
たとえば、被相続人が多額の借入をしているにも関わらず、それに見合う財産が見当たらない場合も調査の対象です。
税務署は、相続税の無申告や過少申告を高い確率で発見できます。
相続財産の目立つ使用
相続財産の目立つ使用も、相続税の無申告が発見される要因です。
相続人が相続後に高額な買い物をしたり、不自然な資産の増加が見られたりすると、税務署の注目を集めます。
たとえば、相続後にローンなしで不動産を購入したり、高級車を現金で購入したりすると、相続税の申告漏れや無申告を疑われる可能性が高いです。
また、相続人の預貯金残高が急激に増加した場合も、調査の対象です。
税務署は、相続人の資産状況や取引履歴を詳細に調査し、とくに相続財産が2億円を超える場合は、より厳しい調査の対象となります。
相続税の無申告と時効期間と適用条件
相続税の無申告は、申告期限から5年で時効を迎えますが、偽りやそのほか不正な行為がある場合は7年に延長されます。
時効が成立すると相続税の申告・納税義務はなくなりますが、税務署はさまざまな方法で相続の発生を把握するため、無申告が発見される可能性は高いです。
無申告が発覚した場合、タイミングによって無申告加算税が5%〜30%の範囲で課税され、延滞税も加算されるため、多額の追加負担が生じます。
そのため、申告期限を過ぎていても早期に自主的な申告をおこなうことで、ペナルティを軽減できる場合があります。
相続税の無申告を防ぐための対策4つ
相続税の無申告を防ぐための対策は、以下の4つです。
- 税理士や弁護士などの専門家へ相談する
- 財産目録を作成する
- 申告期限を確認し早めに手続きする
- 遺産分割協議をスムーズに進める
ひとつずつ解説します。
税理士や弁護士などの専門家へ相談する
相続税申告は複雑で専門知識が必要なため、早めに以下の専門家に相談するのがおすすめです。
- 税理士:相続財産の評価や特例の適用など細かな点まで適切な申告をサポート
- 弁護士:遺産分割や相続放棄など法的な問題に対応
専門家に相談すると申告の必要性を正確に判断でき、相続財産の適切な評価や各種特例の適用可能性を検討できます。
また、申告期限を確実に守れるため、相続が発生したら、できるだけ早く専門家に相談することをおすすめします。
財産目録を作成する
財産目録を作成することで、相続人の遺産調査の手間を省け、相続税申告書作成の負担を軽減できます。
財産目録は、被相続人の相続財産について、種類と金額を一覧整理した書類です。
相続に伴うトラブルを防止する効果もあり、財産目録には「作成日」「署名押印」「プラスの財産」「マイナスの財産」などを記載します。
とくに注意するべき点は、借家権・借地権のような財産意識が薄いものも相続税の申告では評価対象となるため、漏れなく記載することが重要です。
申告期限を確認し早めに手続きする
相続税の申告期限は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10カ月以内です。
期間内に、以下の管理をおこなう必要があります。
- 被相続人の財産と債務の確認
- 遺産分割の実施
- 納付方法の検討
- 申告書の作成
- 必要書類の収集
10カ月は長く感じますが、実際にはさまざまな作業をおこなう必要があるため、時間は多くありません。
申告期限に間に合わない場合、無申告加算税や延滞税などのペナルティが課されます。
また、税金を軽減できる特例が使えなくなる場合もあるため、早めに手続きを始めることで、余裕を持って申告をおこなえます。
遺産分割協議をスムーズに進める
遺産分割協議をスムーズに進めることは、相続税の無申告を防ぐ重要な対策です。
相続税の申告期限は被相続人の死亡を知った日の翌日から10カ月以内ですが、期間内に遺産分割協議が終わらないケースも少なくありません。
遺産分割協議をスムーズに進めるためには、早期に話し合いを始め、財産目録を作成し相続人全員での共有が大切です。
もし遺産分割協議が申告期限に間に合わない場合は「未分割申告」をおこないますが、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例が適用できないなどのデメリットがあります。
また、中立的な第三者(弁護士や税理士)を介入させることも有効です。各相続人の希望を明確にし、柔軟な妥協案の検討が重要です。
相続税の無申告に関するよくある質問
相続税の無申告に関するよくある質問を以下にまとめました。
- 無申告に気付いた場合の対処法は?
- 無申告のリスクと影響は?
それぞれ解説します。
無申告に気付いた場合の対処法は?
相続税の無申告気付いた場合、速やかに「期限後申告」をおこなうことが最善の対処法です。
期限後申告とは、申告期限を過ぎてから相続税の申告書を提出することです。
具体的には、税務署に「期限後申告書」を提出し、加算税と延滞税を含めた税額を納付します。
期限後申告には、以下のメリットがあります。
- 無申告加算税の税率を抑えられる
- 延滞税が軽減される
- 税務調査のリスクを低減できる
ただし、期限後申告をしても申告が遅れれば遅れるほど延滞税は高くなるため、気付いた時点ですぐに行動しましょう。
無申告のリスクと影響は?
相続税の無申告には、以下のような重大なリスクと影響があります。
- 追徴税:無申告加算税と延滞税が課される。無申告加算税は、自主的に申告した場合は5%、税務調査後は最大30%。延滞税は、納付期限から2カ月以内は年7.3%、以降は年14.6%の利率が適用
- 財産の差し押さえ:支払いに応じない場合、国税庁により財産が差し押さえられ、強制的に売却されるリスクがある
- 刑事罰:正当な理由なく申告しない場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されることがある。意図的に申告しなかった場合は、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、または両方が科される可能性がある
- 時効:善意の場合は5年、悪意の場合は7年で時効を迎えるが、税務署の調査により発覚するリスクが高いため、時効を待つのは危険である
無申告のリスクを避けるためには、期限内の適切な申告が重要です。
【まとめ】相続税の無申告を防ぐために専門家へ早めに相談しよう
相続税の無申告が発生した場合、以下のようなペナルティが発生します。
- 延滞税
- 無申告加算税
- 重加算税
- 過少申告加算税
相続税申告における納税期限を過ぎてしまった場合、家計の負担やリスクが増加するため、早めに準備をおこないましょう。
もし相続税についてお悩みの方は、ぜひ翔和会計までお気軽にご相談ください。